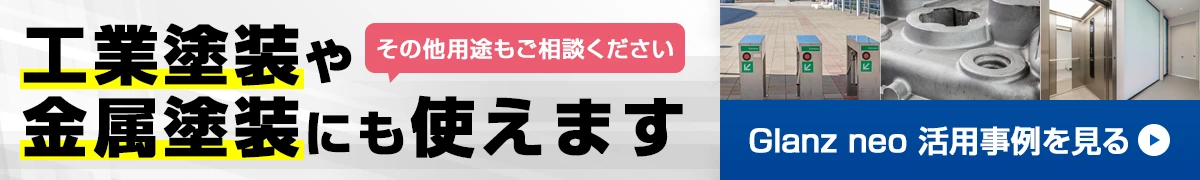いつも弊社ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
さて、本日は皆様に少しワクワクするお知らせと、その「舞台裏」をこっそりご紹介したいと思います。
現在、弊社ではお客様のニーズにさらにお応えすべく、全く新しいコンセプトの新製品開発プロジェクトがスタートいたしました。
製品が皆様のお手元に届く「製品化」までには、企画、設計、試作、評価、量産準備など、非常に多くのステップが存在します。
しかし、そのすべての土台となる、最も重要で、そして最も時間のかかる工程が「基礎実験」です。
0.01%の差を追求する、地道な道のり

新製品の「核」となる技術や性能を実現するため、私たちは日々さまざまな化学物質や原料と向き合っています。特に、弊社としても「初めて触れる成分」を扱う場合、この基礎実験が開発プロセス全体で最も時間のかかる、忍耐力のいる作業となります。
なぜなら、その成分が持つ「個性」をゼロから理解しなくてはならないからです。文献やデータを調査することはもちろんですが、机上の理論と、実際に試作した際の挙動が一致しないのが、ものづくりの世界の常です。
そこで私たちは、気が遠くなるような作業を開始します。
表題にもある通り、それは「成分量を0.01%ずつ調整して試作をつくる」といった、非常に微細な調整の繰り返しです。
なぜそんなに細かく調整するのか?と思われるかもしれません。

例えば、製品の性能を決定づける重要な添加剤の場合、たった0.01%の配合量の違いが、最終的な製品の強度、耐久性、あるいは(私たちの業界で言えば)硬化時間や研磨性などに、天と地ほどの差を生むことがあるからです。
もちろん、すべての成分を0.01%刻みで試すわけではありません。
全体の骨格となるようなベースの成分はまず1%刻み、あるいは5%刻みで大胆に配合を変え、目指す性能の「方向性」を探ることもあります。
研究室の実験台には、配合比がわずかに異なる無数の試作サンプル(ビーカーやシャーレに入ったもの)が並びます。そして、その一つひとつに対して、地道な「性能試験」を繰り返していくのです。
1 + 1 = 2 にならない「配合の妙」

基礎実験で最も難しく、同時に開発者として最も燃える(悩まされる)ポイントが、成分同士の相互作用です。
それぞれの成分の特徴をつかんでも、他の物質が加わると、ガラッと性能が変わったりします。
これは本当にその通りで、
「成分A」単体では、非常に優れた性能(例えば「速乾性」)を持っていたとします。
「成分B」単体でも、素晴らしい性能(例えば「高強度」)を持っていたとします。
では、AとBを混ぜれば「速乾性」で「高強度」な最強の製品ができるかというと、全くそうはなりません。
AとBが互いの長所を打ち消し合って、なぜか「乾燥が遅く、強度の低い」ものができてしまったり、最悪の場合、分離したり固まらなくなったりすることさえあります。
逆に、予想もしなかった「成分C」を加えた途端、AとBがうまく結びつき、性能が飛躍的に向上する「相乗効果(シナジー)」が生まれることもあります。
まさに「1 + 1 = 2」どころか、0にも100にもなるのが、化学配合の世界の奥深さです。
性能試験で「これだ!」という結果が出たと思っても、お客様の使いやすさを考えて別の機能(例えば「粘度調整」)の成分を足した途端、また振り出しに戻る。
この「壁」を乗り越えるために、開発担当者は日夜、無数の組み合わせと配合比を試し続けることになります。
「製品化」というゴールを目指して
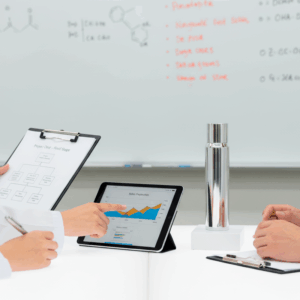
このように、皆様が何気なく手に取ってくださる一つの製品の背景には、開発チームの膨大な時間と試行錯誤が隠されています。「0.01%」の調整に一喜一憂し、「配合の壁」に悩み抜きながらも、私たちが諦めずにいられるのは、すべて「お客様にもっと良いものをお届けしたい」という一心です。
この地道な基礎実験を経て、ようやく「これならいける」という配合の目処が立ち、次のステップに進むことができます。皆様の手元に新製品として届くまでには、ここからさらに何か月もの時間が必要となります。
開発チーム一同、皆様の期待を超える製品を生み出せるよう全力を尽くしてまいりますので、新しい製品の誕生を、どうぞ楽しみにお待ちいただければ幸いです。
今後とも、弊社製品への変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。